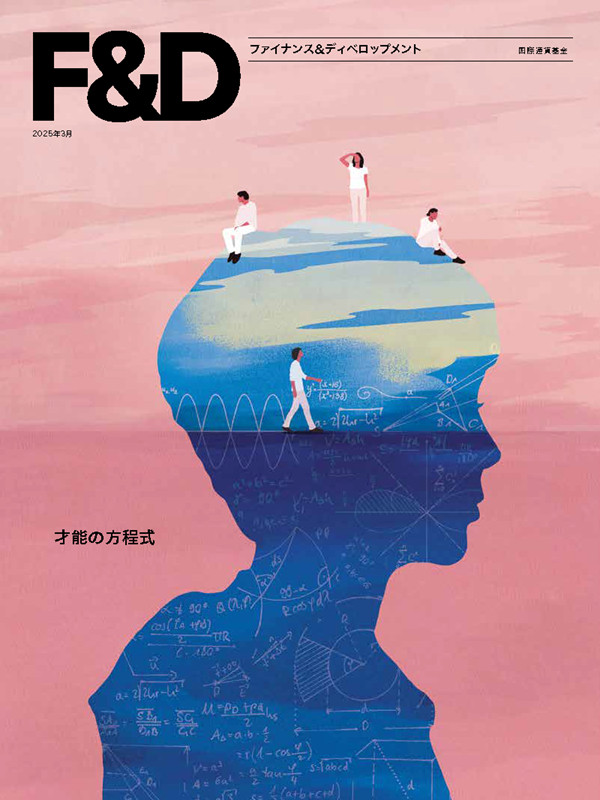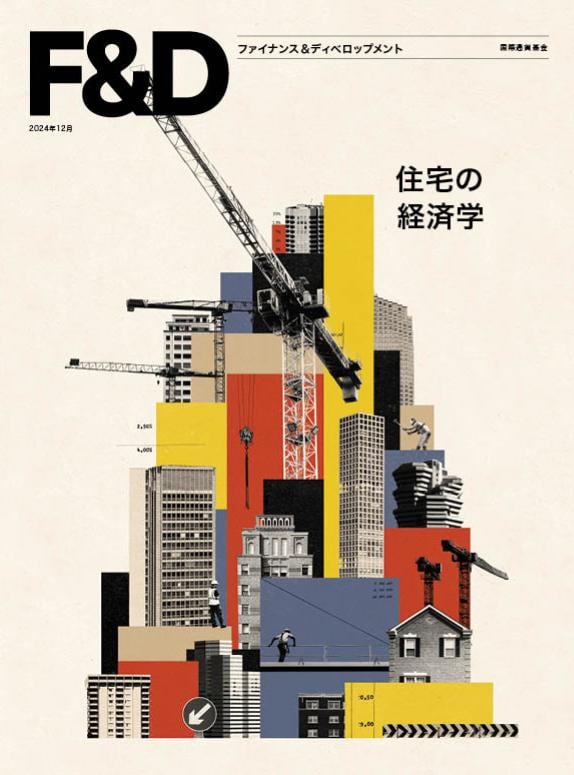ブレトンウッズ会議から80年、IMFは運営上の決定を専門職化し、非政治化しなければならない
もしすでにIMFが存在していなかったなら、われわれはそれを発明せざるを得なかっただろう。パンデミックと世界金融危機という、100年に一度しかないような大惨事に立て続けに二度も見舞われ、各国が国民や組織の存続のために多額の借入れを行った。地球が温暖化して新たな病原体が出現するにつれ、さらなる混乱が生じる恐れがある。その一方で、高齢化する先進工業国と若い発展途上国との機会格差を埋める通常のメカニズムは、貿易や投資の障壁が増えていることが阻害となっている。この断絶拡大によって移民の動きに拍車がかかり、何百万もの人々が、先進国への足がかりを求めて、果敢にも密林を抜けたり海を渡ったりしている。それを受けて、グローバルな統合に反対する声も高まっている。
これらの課題により適切に対処するには、 国際的な財、サービス、資本の行き来が公正に行われるよう支援する政策へと各国を導き、そうした政策を実施しないことの弊害を強調することによって世界貿易機関(WTO)を補完するようなIMFが必要だ。またIMFは、国内政策に対して、特にその国のマクロ経済的安定性を脅かすような政策に対して、独立した意見を提供し、市場の信用を失った国に対しては最後の貸し手としての役割も果たすべきである。IMFは存在しているものの、その時代錯誤な構造では、そうした役割をすべて果たしていく体制が整っているとは残念ながら言えない。
正当性
IMFは、加盟国のニーズに応えるために正当性を要する。IMFが創立した当時は、米国が唯一の超大国で、経済力に恵まれていたために争いにはほとんど巻き込まれずに済んでおり、国際的な財・サービス・資本の行き来に関するルールの執行者として、信頼性があり概ね中立的な存在たり得ていた。米国が主要な決定に対して拒否権を有することや、同盟国のカナダや西欧諸国と共に幹部の任命や運営上の決定を支配していることについて他国が妬むということはなかった。この西側同盟は、最近までほぼ揺るぎないものだった。西側同盟全盛期だった冷戦中には、ソビエト連邦(およびその衛星国)は、軍事超大国ではあったが経済的にはまだ小国で、大部分は世界貿易システムから外れていた。日本は、1980年代後半の絶頂期にはかなりの経済大国だったものの、米国の覇権に挑戦するには米国に依存し過ぎていた。実際のところ、日本は今日、事実上西側同盟の一部となっている。西側の支配が揺るがされるようになったのは、中国が経済と軍事の両面で超大国として台頭してきたごく最近のことである。
もちろん、西側同盟外の国々の代表性の低さに対する不満の声はここしばらくの間高まってきていた。IMF加盟国のクォータは、その国の議決権とIMFに対する出資割当額を表す。ある国がさまざまな状況下でIMFから借入れできる最大額もその国のクォータに比例する。日本のクォータは6.47%で中国の6.4%を上回っている。中国の経済規模は今や日本の4倍以上となっているにもかかわらずである。同様に、インドは経済規模で英国とフランスを追い抜いたにもかかわらず、そのクォータは両国を下回っている。現在では、そのような代表性の低さについて、権勢を維持したいという西側同盟の願望以外の論理的根拠は見出し難い。
再配分が必要な理由
IMFには、正当性が認知されることと、適切なガバナンスが必要だ。それは、ルール交渉を促進しそれらのルールを公平に施行するためだけでなく、IMFのリソースを正しく活用する方法を決定できるようにするためでもある。西側同盟がもはや目的にそぐわなくなったのには、いくつか理由がある。
残念なことに、経済的に、そしていずれは軍事的にも追い抜かれることに対する米国の危惧と、同国の財政余地縮小とが相まって、国内政策の孤立主義傾向が強まってきている。開放性はすべての人に利益をもたらすという考え方を主な動機として審判役を担ってきた米国は、独自の条件による開放性を求めてプレーヤーへと着実に移行してきている。とはいえ米国は、IMFのような組織においてはいまだに審判したがっているのである。また政治的にも、保持している権力を手放すことは欧米のいずれの政権にとっても非常に難しいことだ。権力に固執することがどれだけIMFの有効性を損なうとしてもである。
世界全体で財政力が逼迫しているため、IMFは西側同盟からの追加支援なしで、苦境に陥った国々への融資を行わざるを得ないことが増えている。IMFの潜在的貸倒は、短期的にはいずれの政府の会計上でも顕在化しないため、また、西側同盟は最終的損失を(自国のクォータ割合に比例して)極一部しか負担しないことから、たとえ融資の採算が合わなくても、IMFのリソースを使って苦難を抱える友好国や近隣国を支援したいという誘惑にかられがちだ。IMFの融資には常に政治的要素が含まれてきたものの、IMFは、西側同盟からの外部支援のおかげで、成功する救済プログラムを設計して融資を回収できる公算が大きかった。例えば、メキシコの危機に際しての1994年の救済パッケージでは、米国がかなり大きな割合で寄与した。西側同盟が支配力を行使しつつも自らが投じる資金が大幅に減っているため、IMFは単独で役割を果たしていかざるを得ない場合が増えていく可能性がある。
Loading component...
そして、西側同盟そのものがほころびを見せ始めている。ドナルド・トランプ政権では、カナダや西欧との貿易摩擦が深刻だった。各国政府の政治的構成が変われば、西側同盟内で経済的方向性に関するコンセンサスがますます形成しにくくなることも考えられる。西側同盟がIMFに対する支配力を維持する中でそうなった場合には、意思決定が予測不能になる可能性がある。
クォータと監督
西側同盟が適切なガバナンスを提供し続けることが期待できない場合、相対的経済規模に基づくIMFのクォータ再配分がますます重要性を帯びてくる。しかしながら、それは意図せぬ影響も及ぼしかねない。地政学的相違により世界の分断が進む中で、例えば仮に中国を中心とする同盟ができた場合、西側同盟と密接な繋がりを持つ国に対する融資が妨げられたり、あるいはその逆のことが起きたりする可能性はあるだろうか。ガバナンスの機能不全は、完全な麻痺よりはましなのではないか。
だからこそ、IMFのガバナンスの変更はクォータ改革を伴うべきなのだ。理事会が、すべての融資プログラムを含む、運営上のあらゆる決定について採決するのはやめるべきだ。その代わりに、運営上の決定は、独立した専門職の運営陣が、世界経済の利益になるように行うようにすべきである。理事会メンバーは、幅広い目標を設定し、独立評価室の支援を受けるなどしながら、目標が達成されているかを定期的に検査するようにすべきだ。言い換えれば、理事たちは、企業の取締役と同様にガバナンスに集中すべきなのだ。理事は、運営上の任務を設定し、運営陣の任命や変更を行い、全体的なパフォーマンスを監視して、日常的な決定については運営陣に任せるようにすべきである。
要するに、意思決定を専門職化し非政治化するのが、麻痺に陥る事態を回避する方法なのである。IMFが設立されたとき、ジョン・メイナード・ケインズは、米国の不当な影響力を危惧して、非常駐の理事会を望んでいた。第二次大戦直後の、長距離通信の費用が高く、主に汽船を使った移動には時間がかかっていた当時は、それは、理事会を非業務執行理事会とし、運営陣に権限を与えることを意味していた。ブレトンウッズ会議で、ケインズの案は、米国の交渉役ハリー・デクスター・ホワイトの案により退けられた。今こそケインズ案を再検討する時だ。しかし通信や移動が進歩したことを踏まえれば、明示的に、非常駐理事会は一切運営には関与しないものとすることが必要となる。
IMF幹部については、特定の国や地域に任命権を与えるのではなく、どの候補者が最も幅広いコンセンサスを得るかに基づいて理事会が選定するようにする。そうしたプロセスが政治的になるのは避けられないだろうが、理事会が被任命者の基本資格をいくらか定めている限りは、政治活動は候補者の背後でのコンセンサス形成に役立ち、彼らが確実に効果的に役割を果たせるようになるだろう。
新しいものと古いもの
IMFの劇的な改革に対する政治的障害はかなり大きい。一例として、支配的加盟国が権力を譲ることが、国内に向けて政治的弱さを示すことになるとの懸念があれば、こうした国が権力を譲ることに前向きにならないだろう。加盟国にとっては、最近のクォータ見直しのような段階的措置を講じながら、進歩していると自らに言い聞かせるほうがはるかに楽だろう。難しい決断は次の政権に持ち越され、必然的に再び先送りされる。将来がそうした展開になった場合、IMFという組織は存続していくだろうが、その正当性や世界のニーズに対する関連性は低下するだろう。IMFが発展途上国にとって価値ある組織であることは変わらないと思われるが、世界経済が適応するのを支援していくことにおいては、影響力が大幅に小さくなるだろう。
クォータが経済力を反映するように変化する一方でガバナンスにその他の変更がない場合、やがて中国のクォータが最大となる可能性がある。そうなれば、国際通貨基金協定に基づいて、IMF本部は北京に移転せざるを得ない。ケインズが恐れた政治化が続くだろうが、政治的プレーヤーの顔ぶれやルールも、不満を抱いたり関与しなくなる国々も、一新される可能性がある。
しかしながら、加盟国がクォータとガバナンスを同時に改革した場合には、独立したIMFが、分断化する世界を結集させて重要課題に取り組むことができるかもしれない。西側同盟以外の国々に受け入れられるには、そのような包括的改革が早期になされるべきだ。さもなければ、ついに力関係が変化しかけている時期に西側同盟が影響力を維持しようと試みていると捉えられる可能性がある。
改革されたIMFは、世界経済の変化を考慮しながら、交渉すべき課題の予備的リストを立案するなどして、国際的な財・サービス・資本の行き来に関する新たなルール決定を支援できるだろう。課題の複雑さを踏まえると、IMFの多国間協議の枠組みに基づき少数の国々を集めて初期交渉を行うこともできよう。IMFが十分に幅広い信頼を得られれば、このような新ルールを形成し、その実施を遂行していけるだろう。またIMFは、分析の精度を高め、各国に対してマクロ経済的・対外的持続可能性に関する助言をより適切に行いつつ、より効果的に融資を実施して各国の回復を助けることも可能になるはずだ。
ブレトンウッズ会議から80年が経った今、世界は、IMFを改革して加盟国との関与や各国が抱える課題への対処を向上させていくのか、あるいは行動を起こすことなくIMFを衰退させてしまうのかを決断しなければならない。
記事やその他書物の見解は著者のものであり、必ずしもIMFの方針を反映しているとは限りません。